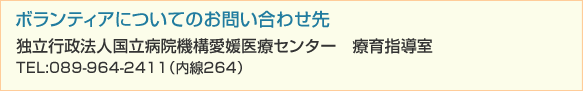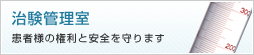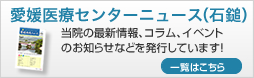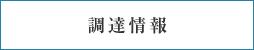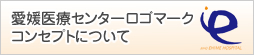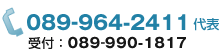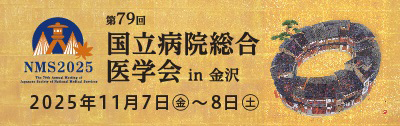ホーム > 重症心身障害児(者)施設について
医療
看護
療育

重度の知的障害及び重度の肢体不自由をあわせもち、重症心身障害児と認定された18歳未満の方及び障害者総合支援法による療養介護サービスの対象であると認められた重症心身障害者(18歳以上)をを受け入れる入院施設です。当院には21病棟(40床)と22、23病棟(各60床)があり、現在160人の重症児(者)の方々の入院療養生活をサポートしています。日々の療養生活には医師、看護師、療養介助員、業務技術員、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など多職種が関わり、重症児・者の方々により良い療養生活を送って頂けるよう努めています。また、在宅療養の方々の支援のために、ショートステイ(短期入所)と外来相談(昼間の療育活動と医療相談など)を行っています。

現在3病棟に160名の重症児(者)の方々が入院されています。設立から40年がたち、入院患者様も高齢化が進んできました。加齢に従い従来の小児疾患中心の診療にかわって成人病の診療の比率が増してきています。痙攣発作や筋緊張のコントロール、感染症の治療の他に、消化管機能障害・慢性呼吸器疾患・骨粗鬆症・がん・糖尿病・婦人科疾患・アレルギーなどの診療も重要となり、対応すべき疾患がますます多岐にわたってきています。
当院では小児科と内科の医師が主治医となり、院内の各科はもちろん近隣の医療施設(愛媛大学病院や専門診療所など)とも連携をとりながら対応を計っています。さらに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などにより四肢機能訓練、呼吸リハビリ、摂食訓練などの各種訓練・リハビリを行っています。
障害者福祉サービス受給者証をお持ちの在宅療養されておられる重症心身障害児・者を対象にして、数日のショートステイ(医療型短期入所サービス)を受け付けています。通常は体調の良いときに来ていただき、1階のポストNICU病棟を利用いただいています。在宅療養の必要物品を持参していただき、吸引・酸素吸入・服薬・栄養注入など必要な介助・医療行為を保護者に代わって行います。短期入所時に体調の不良があった場合にはかかりつけの医療機関に連絡するのが原則ですが、ご希望があれば当院でも対処いたします。
医師 : 松田 俊二、岩井 將、岩田 猛、阿部 聖裕、菊池 知耶、濱田 智子
理学療法士 : 8名
言語聴覚士 : 2名
作業療法士 : 4名

病棟では看護師・療養介助員・看護助手・業務技術員のスタッフが160名の入院患者様の看護を担当しています。患者様も高齢化しまた重症化する中で患者様・家族が安心して医療が受けられ、満足した療養生活が送られるよう日々取り組んでいます。看護は、日常生活の援助が中心になりますが、それぞれ専門の理学療法士・作業療法士から指導を受け呼吸リハビリや摂食機能訓練・ムーブメント療法等を行っています。

<呼吸リハビリ>

<摂食機能訓練>

<ムーブメント療法>

長期の入院生活を送る重症心身障害児・者にとって、日常生活の質の向上(生活を豊かにすること)を図ることは重要です。そのために療育指導室(児童指導員、保育士)が中心となって種々の活動を行っています。快い感覚刺激、他の人々との楽しい交流、作業をとおした機能回復刺激などの療育活動を通し、成長・発達や、豊かな日常生活を支援します。
児童指導員 : 3名
保育士 : 4名+保育士(非常勤)1名
当院では平成2年より、在宅で療養を続けられている障害者の方々を対象として、医療上の相談と療養活動を「外来相談」という名で行っています。手続は一般外来受診と同様です。現在、約20名の方が登録され、原則、毎月第2木曜日、10時から15時の間、訓練棟において、医療相談(専門医による発達相談、神経・痙攣相談、アレルギー相談など、投薬、検査など)と療育活動(児童指導員、保育士によるニーズに あった療育活動など)を行っています。また、外部からの協力を得て、摂食指導や作業療法なども行っています。
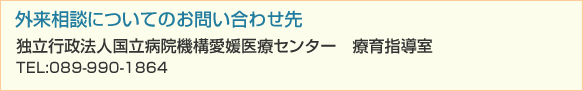

当院では施設開設の4年後の昭和48年よりボランティア活動が続けられています。長期入院の重症児・者にとって、外部の人々と接することは有意義であり、大きな楽しみでもあります。現在、ボランティアグループに毎月1回病棟訪問していただいており、外来相談でもボランティアの方々に協力していただいています。今後もボランティアの方々を受け入れていきますので、興味のある方は気軽にお声かけください。